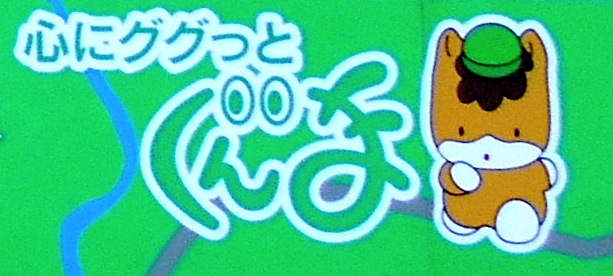
〇 与謝野晶子のみなかみ町への旅
○ 諏訪峡遊歩道
○ 与謝野晶子歌碑公園
与謝野晶子の足跡を書簡等からまとめました。
・昭和 6(1931)年9月4日〜6日
法師温泉に夫婦3泊。
法師温泉から駕籠に乗って三国峠を訪問。
・昭和 7(1932)年5月10日〜11日
湯原温泉菊富士別館(現在「サニックス水上壱番館」)に夫婦泊。
5月11日に越後の湯沢温泉へ向かう。
・昭和 9(1934)年10月25日〜26日
湯檜曽温泉林屋旅館に夫婦泊。
・昭和14(1939)年11月4〜5日
猿ヶ京温泉笹の湯泊、5日に法師温泉へ日帰り。
『冬柏』上越遊草(昭和7(1932)年5月)
多くの歌が掲載されています。
『白桜集』奥上州(昭和17(1942)年9月)
与謝野寛と共に歩んだ思い出の挽歌が多いです。
笹の湯(ダムに沈んだ猿ヶ京温泉)と法師で30歌掲載されています。
<諏訪峡めぐり案内図>
道の駅水紀行館から与謝野晶子歌碑公園まで、歌碑を観賞しながらのウォーキングしました。
道の駅みなかみ水紀行館駐車場から利根川に沿って遊歩道が続いています。
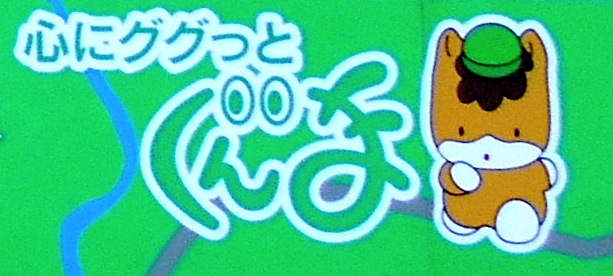
<足湯>
足湯の前を通ります。
軽トラックでの運搬湯です。
<桜並木>
多くの方々が桜を寄贈しています。「櫻内義雄様」の名も見受けられました。
<双体道祖神>
最初に双体道祖神があります。
<橋を渡る>
階段を下りて橋を渡ると、利根川沿に歌碑5基が続きます。
<桜並木の5基5首の歌碑>
昭和6(1931)年9月4日から夫婦で法師温泉に3泊した時の作と、
昭和7(1932)年5月10日に夫婦で湯原温泉に泊まった時の作です。
「石多く 屋根に置くなり 利根郡 いづれの家も 棋盤のごとく 晶子」
晶子は碁を打つのかな?孫の与謝野馨氏は政界きっての囲碁の強豪として知られていました。
「晶子詩篇全集」(與謝野晶子)に「空しき日」と題する詩があり、
この中に「棋盤(ごばん)」が出てきます。「棋盤」と書いて、「ごばん」と読ませています。
「男は独り棋盤に向ひて五目並べの稽古してありしと云ふ。」(「空しき日」より抜粋)
短歌は棋盤とあるので、当然のごとく私は囲碁を想起しましたが、
晶子は五目並べを頭に浮かべていたのかもしれませんね。
囲碁は陣地取り、五目並べは石の連続です。
屋根の上の石は、囲碁より五目並べの石のほうがイメージに合っている気がします。
「寶の湯 これより奥に ありと云ふ 利根餘吾橋も 寂しかりけれ 晶子」
法師温泉には泊まりと日帰りで2度も行ったけど、宝の湯には行かなかったのですね。
「入る方は 谷川岳か わが立ちし 三国峠か うら若き月 晶子」
「小日向の 湯場の灯ともる 刻ならん 川の暗きに 山すもも散る 晶子」
湯原温泉にお泊りですね。
「朝焼も 夕映も皆 をさめたる 利根水上の 十里乃紅葉 晶子」
秋だとすれば、笹の湯に行った時の途上かな?調べきれていません。
<谷川岳八景3番>
立看板を笹笛橋方向へ曲がります。ここまで水紀行館から600mです。
「谷川岳八景3番」は、写真ではなく絵が掲示されていて、情緒ありますね。
利根川と谷川連峰が一望できるスポットです。
<岩の群れ〜歌碑>
「岩の群れ おごれど阻む ちからなし 矢を射つつ行く 若き利根川 与謝野晶子」
与謝野晶子歌碑公園が2009年にオープンする前から笹笛橋袂にあります。
昭和57(1982)年11月1日建碑です。
昭和7(1932)年5月10日、菊富士別館に宿泊しています。
<笹笛橋/笹笛童子公園> みなかみ町小日向
笹笛橋を渡ると笹笛童子公園です。
笹笛を吹く少年と少女の笹笛童子のブロンズ像があり、「笹笛橋」の歌詞が掲示されています。

(説明板)
「名勝 諏訪峡
諏訪峡は、小日向川合流落合より始まり、下流銚子橋の間で、上流部は川床を激しく激流となって流れ川床を大きく浸食し「龍ヶ瀬」の奇観無数や「甌穴」(カメ穴ともいう)などが形成されて、下流部は、ゆったりとした流れに変わり「瀞」となっている。
笹笛橋下附近の岩脈には、海底火山の活動があった。海底火山の流失した「溶岩を示す模様」が見られる。また、大きな「甌穴」などいくつか見られる。
諏訪峡一帯の岩質は、変質石英粗面岩、同質凝灰岩・凝礫岩を主とし、わずかに砂岩・頁岩をはさむ。諏訪峡は模式的露出地である。
火砕岩は、すべて変質作用のため緑色?淡緑色を示し、溶岩流は、灰緑色?黄褐色を呈す。また、石英粗面岩は流状構造、球顆構造、杏仁状構造が発達している。杏仁は数センチメートルの径をもつものもあり、多くは玉髄、蛋白名、緑泥石等からなっている。」
平成21(2009)年に与謝野晶子歌碑公園が作られました。
利根川沿の歌碑を含めると、11基の詩歌碑(12首、2詩)があります。
(案内板)
「与謝野晶子歌碑公園
与謝野晶子(1878年?1942年)は、大阪府堺市に生まれた。(中略)
晶子はみなかみ町を4度、訪れた。昭和6年秋に法師温泉、昭和7年春に水上温泉、昭和9年秋に湯檜曽温泉、昭和14年秋に猿ヶ京温泉を訪れ、寛135首、晶子221首を歌っている。
ここ諏訪峡には昭和7年5月10日に訪れ、若き利根川、「山吹」などみなかみ町の花の歌など24首歌った。
この公園は、3つの歌のゾーンに分かれている。」
「この六首は、寛・晶子六女 森藤子氏の書です。」
「この二つの詩は、明治45年のパリ留学の時から被るようになったつば広の帽子を近代精神のシンボルとして碑に表しました。」
〇夫婦碑(天使の羽根のレリーフ)3首
「利根の洲の 白きあたりに かじか鳴き 温湯川より
夕風のぼる 晶子」
「前の山 なほ暗けれど 三つばかり 朱に染む奥の
あけぼのの山 寛」
「行く水の 轟くままに みづからの 声を忘れて 渓にあるかな 寛」
(英訳 ジャニー・バイチマン)
〇夫婦碑(椿の花のレリーフ)3首
与謝野夫婦は椿を愛したことから、椿の花のレリーフなのでしょう。
出典は「冬柏」上越遊草(昭和7年5月)
「日のひかり 渓に香りて 虎杖と 蓬にまじる 山吹の花 寛」
「吊橋と 舞へる燕を 中にして 両つの岸に すもも花咲く 晶子」
「岩の群 おごれど阻む 力なし 矢を射つつ行く 若き利根川 晶子」
(英訳 ジャニー・バイチマン)
〇椿のモニュメント
出典は「青海波」(明治44年)。晶子親筆。
「七つの子 かたはらに来て わが歌を すこしづつよむ 春の夕ぐれ 晶子」
〇帽子のレリーフ
与謝野晶子詩碑。晶子愛用の丸帽子のレリーフです。
明治45年のパリ留学の時から被るようになったつば広の帽子の写真を載せます。
「山の動く日
山の動く日きたる、
かく云えど、人これを信ぜじ。
山はしばらく眠りしのみ、
その昔、彼等みな火に燃えて動きしを。
されど、そは信ぜずともよし、
人よ、ああ、唯だこれを信ぜよ、
すべて眠りし女、
今ぞ目覚めて動くなる。」

〇帽子のモニュメント
与謝野晶子詩碑。晶子愛用の丸帽子型です。
「君死にたまふことなかれ
(旅順口の包囲軍の中に在る弟を歎きて) 晶子
あゝをとうとよ、君を泣く、
君死にたまふことなかれ、
末に生れし君なれば
親のなさけは勝りししも
親は刃をにぎらせて
人を殺せと教へしや、
人を殺して死ねよとて
二十四までを育てしや。」